|
Hα太陽像の撮影
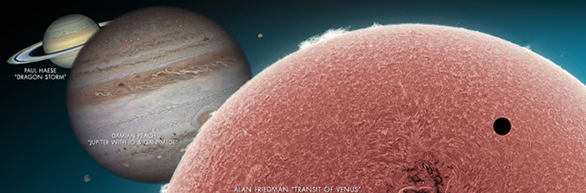


『太陽のプロミネンスや彩層面は、どのように撮影すればよいのか?』ダイナミックな太陽姿を観るだけでなく、撮影もしてみたいユーザーからよくいただくお問合せのひとつです。
ここでは白色光による撮影を除き、Hα太陽望遠鏡、Hα太陽フィルターを使って、太陽の彩層面を撮影する方法を、できるだけ簡単に解説します。
まずは、Hα太陽望遠鏡・フィルターは、いずれも「656nm」の水素波長だけを取り出すことで、主に水素波長を放つ太陽の彩層面を観望・撮影する機材であることをご理解ください。したがって、カラー素子を内蔵した一般的なデジタルカメラでは、結果的にHα線を受光できる赤の画素が全体の1/4になってしまうといわれます。そため、カラー素子で撮影した太陽のHα画像はなんとなくボケたような結果になるか、諧調不足でザラザラとした画質になります。
そこで、今現在、Hα太陽像を撮るカメラのうち、最もおすすめのものが、Hα線に感度が高く、PCへの動画取込みにより画像処理が容易なモノクロビデオカメラです。以下、一般的なHα太陽像の撮影方法を解説しますが、撮影結果は、その日の大気の影響で大きく左右され、画像処理の方法も千差万別です。ご自身の工夫と感性に任せ、楽しみながら挑戦してみてください。
1. 動画取込: PCにインストールしたキャプチャーソフトにより、太陽面がシーイングの影響で絶えず揺れたりぼけたりしている状態を動画で撮影し、露光条件や出力フォーマット(画像処理ソフトが受け付ける)などを設定して取り込み、動画ファイルを作成します。
2. スタック処理: PCにインストールしたスタックソフトにより、揺れたりボケたりしている動画から、ボケが少ない領域だけを抽出し、位置補正しながら加算平均することで静止画に変換します。スタックソフトのRegiStax、AviStackなら、ほぼ自動処理されます。
3. 画像処理: PCにインストールしたPhotoshopなどの画像処理ソフトにより、トーンカーブ処理で色合いを表現し、細かい構造のシャープネスやコントラス をさらに強調したり、着色したりします。また、プロミネンスの輝度は太陽ディスクに比べ低いため、それぞれを分けて処理する方法や、それぞれ異なる露出時間で撮り込む方法など、ユーザー独自で処理します。
|